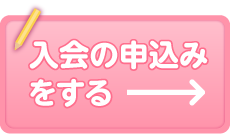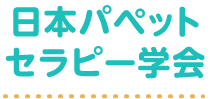被災地支援活動 その8
2018年01月20日
ようこそ 「Puppet Therapy Cafe」へ
今回も、前回の続きのお話しです。
第4回目の被災地支援活動は、2014年11月に行われました。
この時は、ヒブッキープロジェクトチームとニコニコ大使と共同で、
宮城県山元町のふじ幼稚園で再度行われました。
これは、同じ場所に繰り返し訪問することの重要性からでした。
そして、ヒブッキーが子どもたちの日常生活に大切な存在として
活躍している姿が確認されました。
次回に続く
カテゴリ:被災地支援活動




 腹話術師、人形療法士、音楽家である末永久志(スーちゃん)のホームページ「夢のおもちゃ箱」
腹話術師、人形療法士、音楽家である末永久志(スーちゃん)のホームページ「夢のおもちゃ箱」 ダニエラ・ハダシーさん(Daniela Hadasy、イスラエル)のホームページ
ダニエラ・ハダシーさん(Daniela Hadasy、イスラエル)のホームページ ソックスパペット工房のホームページ
ソックスパペット工房のホームページ 腹話術師アンディのホームページ
腹話術師アンディのホームページ てるぼのホームページ笑顔がいっぱい腹話術『てるぼ』
てるぼのホームページ笑顔がいっぱい腹話術『てるぼ』 スマイリー・チバ仙台の腹話術師
スマイリー・チバ仙台の腹話術師 笑顔と癒しのパペットセラピー腹話術師矢崎育子
笑顔と癒しのパペットセラピー腹話術師矢崎育子