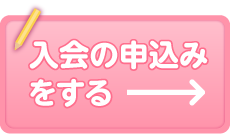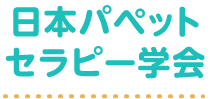大学生 パペットと出会う
2025年03月18日
 先日、明星大学の心理学専攻の学生さん相手にパペトセラピーの講演をさせていただきました。「心理臨床に生かすパペットセラピー」という題で、約40名ほどの学生さんの前でお話をさせてもらいました。
先日、明星大学の心理学専攻の学生さん相手にパペトセラピーの講演をさせていただきました。「心理臨床に生かすパペットセラピー」という題で、約40名ほどの学生さんの前でお話をさせてもらいました。
前半はパペットの機能などの説明や教育相談の中での事例などのお話をしました。みなさん真剣に話を聞いてくれていました。が、もちろん中には眠そうな顔をしている人もいました(笑)
最後に質問を取りましたが、「パペットを使ったロールプレイではパペットをどのように選んだのですか」「思春期の子どもにもパペットセラピーは有効なのでしょうか」「親子関係が崩壊に近い家庭でも親子でのパペット遊びは有効に機能するのでしょうか」など、自分が心理の現場に行ったときに活用しようと思ってくれているのかなと思えるような質問をいくつも受けました。また、1人の学生さんが、卒業論文として、ペット(犬)を飼育することによる母親の養育態度の変化を研究したとのことで、「母親の子どもに対する態度が明らかにソフトになった」という結果が、パペットを使うことで母親が子どもに優しくなれることがあるという講演の中での話と共通するということを指摘してくれました。そんな風に自分の臨床体験を頭に置きながらこの講演を聞いてくれたことがうれしかったし、ぼく自身も勉強になりました。
休憩を挟んで、後半は簡単なパペット入門ワークショップ。パペットが人数分用意できなかったので、目玉をかいたシールを手に貼って、それでパクパクやってもらうことにしました。初めみんな照れていましたが、何度かやっているうちにだんだんほぐれてきました。最後は「2人組になって1人クライエント役の人にセラピスト役が合わせてパペットでおしゃべりしたり遊んだりしてみてください」という課題になりました。みんな子どもに戻ったようで嬉々としてパペットのやりとりを楽しんでいて、「そろそろ終わりにしましょうか」といわなかったらいつまでもやっているような様子でした。
心理臨床での十分な実践やノウハウがないのをちょっと残念に思いましたが、今日お話を聞いた人が少しでも興味を持ってくれて、研究を深めてくれる人が出てくれたらうれしいなあと思いました。
パペットセラピーを学生さんに紹介する機会を作ってくださった明星大学の石井雄吉先生にも感謝したいと思います。(deyama)




 腹話術師、人形療法士、音楽家である末永久志(スーちゃん)のホームページ「夢のおもちゃ箱」
腹話術師、人形療法士、音楽家である末永久志(スーちゃん)のホームページ「夢のおもちゃ箱」 ダニエラ・ハダシーさん(Daniela Hadasy、イスラエル)のホームページ
ダニエラ・ハダシーさん(Daniela Hadasy、イスラエル)のホームページ ソックスパペット工房のホームページ
ソックスパペット工房のホームページ 腹話術師アンディのホームページ
腹話術師アンディのホームページ てるぼのホームページ笑顔がいっぱい腹話術『てるぼ』
てるぼのホームページ笑顔がいっぱい腹話術『てるぼ』 スマイリー・チバ仙台の腹話術師
スマイリー・チバ仙台の腹話術師 笑顔と癒しのパペットセラピー腹話術師矢崎育子
笑顔と癒しのパペットセラピー腹話術師矢崎育子